こんにちは。マツイkoubouの タカキ マツイ です。
今回は、家系図を作成するためにまず何から始めるかというお話です。
家系図作成には大きく2パターンに分けられます。
①戸籍をたどって作成する=江戸時代後期の祖先までさかのぼれる
ただし、戸籍が廃棄されていたり、
戦災や事前災害のために戸籍が滅失している可能性もあります。
②お墓(菩提寺)や過去帳などを調べたり、図書館などに行って文献を調べたりして
足を使って調べる=家系にもよりますが、最終的には「氏のルーツ」を知ることができる

①の場合、比較的簡単に調べることができるので
まずは①で家系図を作成し、興味がもっと増したら②の方法で
本格的な家系調査をすることをおすすめします。
①の場合は、戸籍の取り寄せのみで家系図を作成することができます。
戸籍には大きく5種類の戸籍があります。
1、明治19年式
2、明治31年式
3、大正4年式
4、昭和23年式
5、平成6年式
があり、いま手に入る戸籍で一番古いものが
明治19年式です。
(平成22年までは、戸籍の保存期間が80年だったため、
役所によってはすでに廃棄している可能性もあります。現在は150年間の保存義務があります)
明治19年式までさかのぼることができれば、江戸を生きていた
先祖の名前を知ることができます。
詳しく知りたい方は、家系図の作り方を
簡単に説明してくれている書籍が本屋や図書館においてありますし,
家系図の作成を取り扱っている行政書士に聞いてみるのも
いいと思います。①の家系図の作成については
家系図作成をうたっている行政書士ならばよく知っているはずです。

上の写真は、作成した家系図を装幀してもらったものです
それでは、また。
タカキ マツイ
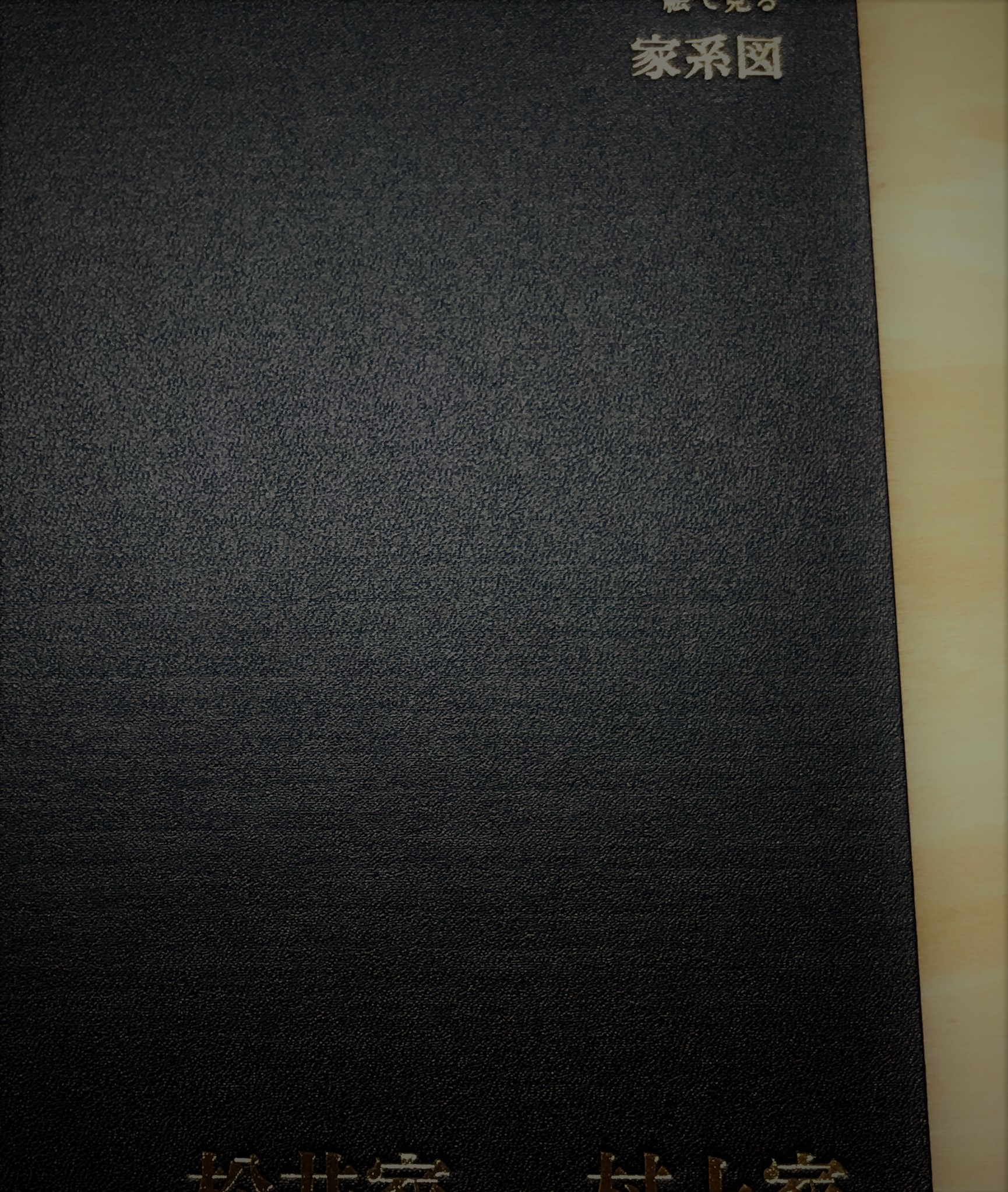
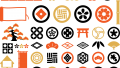

コメント